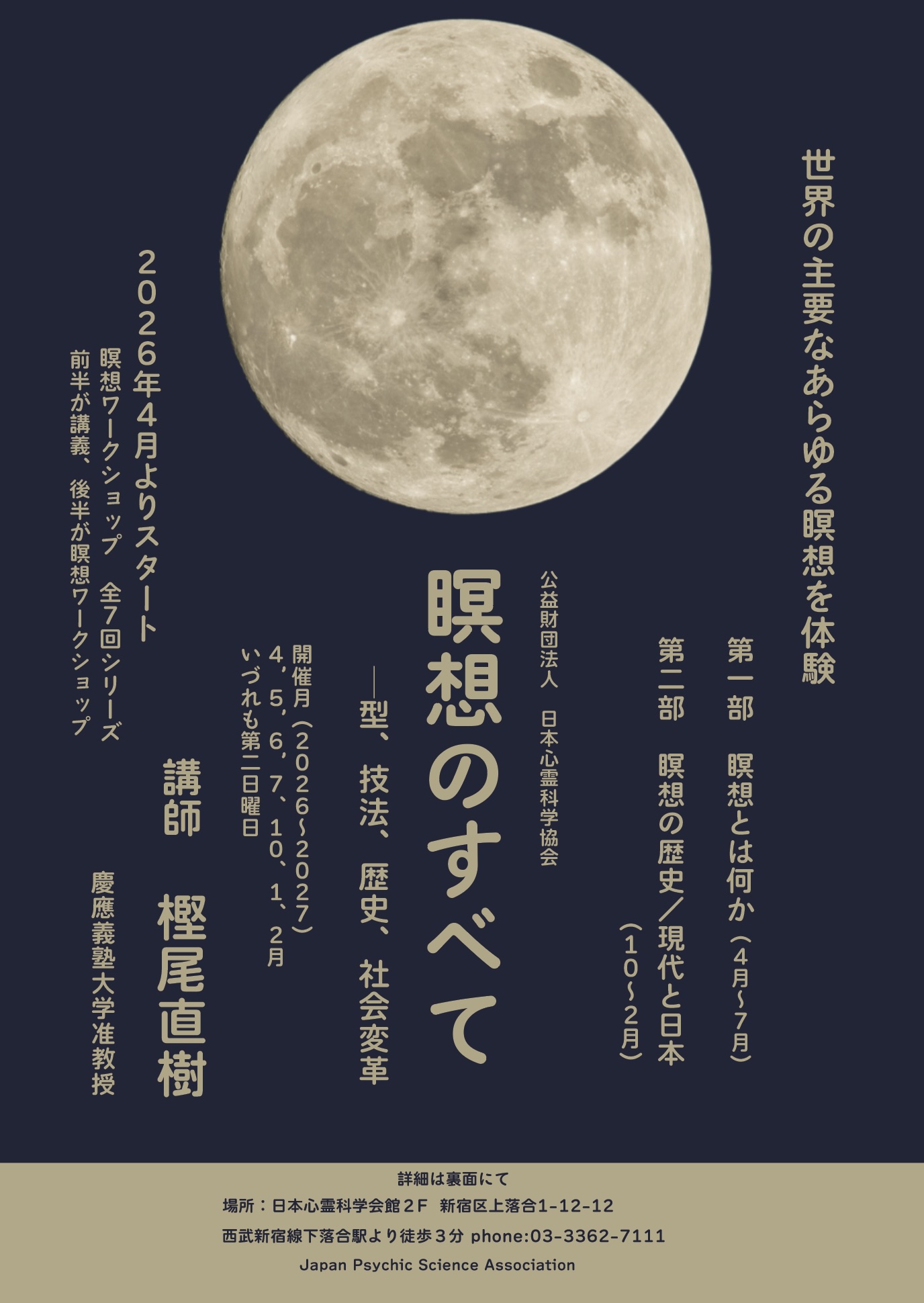瞑想ワークショップ 全7回シリーズ
「瞑想のすべて-型、技法、歴史、社会変革」
講師 樫尾直樹 慶應義塾大学准教授
第一部 瞑想とは何か
4月 ①瞑想の一般理論:WS 坐禅
5月 ②瞑想の身心気技法:WS 瞑想における呼吸と身体の使い方
6月 ③瞑想複合:WS 動的瞑想1 瞑想における丹田/チャクラ
7月 ④悟りとは何か:WS サマタ/ヴィパッサナー
第二部 瞑想の歴史/現代と日本
10月 ⑤沸き起こる力とダンスからの一万年:WS 動的瞑想2 丹田活性化ダンス
1月 ⑥「道」としての瞑想日本:WS 鎮魂、禅、武道的身体運動
2月 ⑦瞑想の統合と共同性の始原へ:WS ダイナミック瞑想、経絡体操、マインドフルネス
【全7回 一回二時間の実修。20 名ずつの⼆回制】
◆2月6日(金)11時からお申し込み受付開始◆
受講料:会員:22000円、一般25000円(まとめてのお支払いになります)
場所:日本心霊科学会館 2F
事務局:03-3362-7111
A)13:00〜15:00
B)16:00〜18:00
※A、Bどちらかの時間帯をお選び下さい。
「お申し込みについて」を必ずお読み下さい。
講師よりワークショップについて
瞑想的経験の諸相」(2024年度)では、瞑想の諸類型を中心に説明し、瞑想の理論と歴史について扱った。「瞑想の技法」(2025年度)では、坐法・ムドラー・丹田・背骨を主題として、瞑想実践における見える肉体の使い方を通した不可視の身体の起動と活性化について扱った。2026年度では、過去2回の瞑想論シリーズを止揚し、「瞑想のすべて」と題して、十全な過不足ない瞑想論を展開する。かつこれまで深く扱って来なかった瞑想が実現する「悟り」の内実について、そして、瞑想の起源であるダンス、瞑想日本の「道」の実践、および動的瞑想と現代における瞑想の想像的創造と社会変革の可能性についても講義する。
本講演「瞑想のすべて」のシリーズは、これまで通り、前半が講義、後半が瞑想ワークショップを実施するが、特に呼吸を中心とした身体の使い方・動かし方に力点をおいて、ふだんの生活における身体の動かし方を改善することを促し、その結果、瞑想の格段に深まるような、言葉の真の意味でディープな実修を行いたい。予定表のように、各回のテーマの中心となる瞑想や瞑想技法を実修するが、参加者の状態や関心、進捗状況などを毎回適宜判断して、臨機応変にメニューを組み立てたい。
本講演に参加して、世界の主要なあらゆる瞑想を体験することで、世界の諸宗教の核心に触れ、世界を自由に旅することが可能になるだろう。みなさまのご参加を期待しています!
食事は3時間前に。無地の着衣(模様なし、文字なし)、できれば丸首のTシャツ。ベルト無しのズボンを着用してください(動きやすい服装で)。アクセサリー類は身に着けない。裸足(もしくは5本指ソックス)。実修中はマスクをつけない(やむを得ない場合を除く)。できれば、ヨガマット持参(無い場合は、会場の座布団を使用)。
7回一括でのお申し込みになります。お申し込みの際に、受講料を添えて事務局窓口までお申し込み下さい。また、受講希望の時間帯(AもしくはB)をお選び下さい。電話でのお申し込みの場合は、お申込み後、数日以内にお振込をお願いいたします。お振込みがない場合は、自動的にキャンセルとなります。また、ご入金後のご返金はいたしかねますので予めご了承ください。
予約・問い合わせ 事務局 03(3362)7111
【お振込み先】公益財団法人 日本心霊科学協会
★ゆうちょ銀行
口座記号番号00150-3-37677
★他金融機関からの振込用口座番号
019(ゼロイチキュウ)店 当座 0037677
 慶應義塾大学文学部准教授。宗教学者。慶應義塾大学経済学部卒、同法学部政治学科中退。東京大学大学院人文科学研究科宗教学・宗教史学専攻博士課程修了。早稲田大学人間科学部(文化人類学)助手、東京外国語大学外国語学部日本語学科助手、フランス国立高等研究院(宗教学部)客員教授、同科学研究センター(GSRL)共同研究員、韓国東西大学大学院(日本学)客員教授などを経て現職。経済学、政治学、宗教学、文化人類学、日本学、社会学、民俗学・・・、人文社会科学の諸領域を渡り歩く<マルチ・アカデミック・ストレンジャー>。毎日3時間の道教瞑想を日課とし、身体実践を通じた宗教研究(比較瞑想論)を提唱している。慶応瞑想研究所(マインドフルネス・センター)主宰。著書に『スピリチュアリティ革命』(春秋社)、『スピリチュアル・ライフのすすめ』(文春新書)、『慶応大学マインドフルネス教室へようこそ!』(国書刊行会)、『マインドフルネスがよくわかる本』(秀和システム)、”Spirituality as a Way: The Wisdom of Japan”(Kyoto University Press/Trans Pacific Press)など多数。
慶應義塾大学文学部准教授。宗教学者。慶應義塾大学経済学部卒、同法学部政治学科中退。東京大学大学院人文科学研究科宗教学・宗教史学専攻博士課程修了。早稲田大学人間科学部(文化人類学)助手、東京外国語大学外国語学部日本語学科助手、フランス国立高等研究院(宗教学部)客員教授、同科学研究センター(GSRL)共同研究員、韓国東西大学大学院(日本学)客員教授などを経て現職。経済学、政治学、宗教学、文化人類学、日本学、社会学、民俗学・・・、人文社会科学の諸領域を渡り歩く<マルチ・アカデミック・ストレンジャー>。毎日3時間の道教瞑想を日課とし、身体実践を通じた宗教研究(比較瞑想論)を提唱している。慶応瞑想研究所(マインドフルネス・センター)主宰。著書に『スピリチュアリティ革命』(春秋社)、『スピリチュアル・ライフのすすめ』(文春新書)、『慶応大学マインドフルネス教室へようこそ!』(国書刊行会)、『マインドフルネスがよくわかる本』(秀和システム)、”Spirituality as a Way: The Wisdom of Japan”(Kyoto University Press/Trans Pacific Press)など多数。